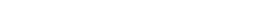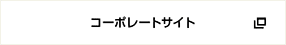コンクリート打設とは?打設手順や工法、打設する時の注意点まで詳しくご紹介!
人々の生活を支えるコンクリート建設物を作る際に実施する、コンクリート打設作業は作る建設物の大きさ、区画や周囲の環境、条件によって意識すべきポイントが数多くあります。知識やスキルだけではなく、携わってきた現場の経験が職人の技術をつちかい、長く安全に使用できるコンクリート建設物が作られてきました。
白岩工業では鉄道工事や高速道路工事、ダム、上下水道といった大規模なインフラ設備の躯体工事・コンクリート打設作業に携わっています。今回は躯体工事の中でもコンクリート打設に焦点を当てて、打設手順や工法、打設する時の注意点まで詳しくご紹介していきます。
躯体工事についてはこちらでもご紹介していますので、あわせてご覧ください。
躯体工事ってどんなもの?白岩工業で行っている躯体工事のポイントを詳しく紹介!
白岩工業で行う躯体工事についてインタビュー!工事で気をつけているポイントをお聞きしました!
コンクリート打設とは

コンクリートの打設とは、固まっていない生のコンクリートを流し入れ、全ての建設物において基礎となる部分を作る工事のことを指します。コンクリートを打設する前には工事を行う現場の調査からはじまり、防水工事・鉄筋工事・型枠工事・足場工事・支保工工事など躯体工事が行われています。
流し入れる準備が整って初めて、コンクリート打設を行える環境になるのです。
コンクリートの打設は建設物の品質・強度に直結する作業であり、特に夏場はコンクリートがすぐに固まり始めてしまうため、作業を始めると後戻りができないことが大きな特徴です。長く安全に使い続けられる設備を作るためには、建設物が丈夫であることが求められるため、不備なく工事を進める必要があるでしょう。
コンクリート打設作業に限らず、工事現場ではQCDSEというQ:Quality(品質)、C:Cost(原価)、D:Delivery(工程、工期)、S:Safety(安全)、E:Environment(環境)を重視した考え方を大切に進められています。質の高い建設物を、決まっている予算、工期を遵守して、建設現場における安全性と環境にも配慮しながら完成させることの重要性を意味しています。
コンクリート打設の手順
コンクリート打設は現場の施工計画書に沿って行われています。現場によって周辺の環境や、施工に必要な条件、コンクリートの量から使用される工法もさまざまです。
例えば、高所か地下か、都市部か山間部かといった場所によっても気をつけるべきポイントは大きく異なります。
今回はまず、コンクリート打設の手順を詳しくご紹介していきます。
コンクリートの検査
コンクリートの安全性を確認するため、打設前には必ず生コンクリートが施工計画で提出した品質であることを検査する必要があります。検査を通し、打設を行うのに適した生コンクリートであることを確認しています。検査を行う頻度も明確に定められており、打設を始める時だけではなく、構造が変わる時や工事現場の規模に合わせて何度も検査を行うことがあります。
検査ではコンクリートの硬さ、空気量、水分、塩化物量の規定などそれぞれの数値が規格値の中に収まっていることを確認していきます。長く使用するコンクリート建造物を作る上では検査は欠かせません。検査を実施していないコンクリートを使用することは認められていないため、必ず検査に合格してから打設作業を行う必要があります。
コンクリートを流し入れる準備
コンクリート打設を行う前には、打設準備や打設に必要な資材の搬入といった工程が必要不可欠です。
特に建設物を作るために大切なことは寸法です。コンクリート打設を行う前には必ず、建設物の測量とマーキングを行い建設物を作る範囲を明確にわかりやすくするための作業を行います。寸法は元々図面に記載されていますが、人の手で作る物において1ミリも狂わずに100メートルのものを作り上げることは難しいといえるでしょう。
そのため、工事を始める前に図面だけでなく、計画書、元請さんに工事の範囲を表す規格値を確認してから工事に入ります。その上で下記のような工程を経てコンクリートを流し入れることができます。
• 鉄筋工事:コンクリートの強度を高めるための骨組みとなる、鉄筋を組み立てる工事
• 型枠工事:コンクリートを流し込むための型を設置する工事
• 足場工事:工事に必要となる安全な足場を設置する工事
• 支保工工事:建物の上階を支えるための仮設支柱を設置する工事
コンクリートの打設・締固め
コンクリートの打設では、型枠の中へ数回に分けてコンクリートを流し入れていきます。
コンクリートの打設は一度で終わる作業ではありません。建設物の大きさや高さにもよりますが、流し入れる高さには通常1.5m以内から落とすように制限されています。これはコンクリートが砂やセメントなどさまざまな材料が混ざっていることから、材料分離を起こしてしまう危険性があるためです。
具体的には、コンクリートは砂利、セメント、水などで構成されていますがそれぞれ重さ(比重)は異なるため、高い場所から落とすと重いものが下に固まってしまいますよね。その場合、コンクリート材料が分離し、比重の大きい砂利などの骨材が下に偏って層となり、砂利の層に隙間ができる、ジャンカと呼ばれる状態となります。
コンクリートにジャンカができてしまうと、その部分から水分や炭酸ガスが浸透しやすく、コンクリートの骨組みとなる鉄筋が二酸化炭素によって酸化し錆びて耐久性が低下する現象が起きてしまいます。
また、締固めではバイブレーター(振動機械)を使用し、型枠のコーナー部分までコンクリートが充填されていることを確認します。締固めを行うことによって、コンクリート内部の空気をなくし、より密度を高めることで強度を向上させる目的もあります。(逆に言うと、しっかり空気を抜かないと高さでお伝えしたのと同様にコンクリートに隙間ができてしまい、コンクリート表面のひび割れやコンクリートの鉄筋が錆びて耐久性が低下してしまいます。)
型枠内に充填されていることが目視で確認できない狭い箇所や暗い場所では、センサーやカメラを使用し、確実な品質を維持していきます。
コンクリートの仕上げ
コンクリート打設では、型枠を取り外した後に補修がない状態であることが理想です。補修が必要な際もコンクリートの強度や見た目において規約が定められているため、元請さんに相談をしながら進めることが求められます。
コンクリートの不備は、代表的な物では下記のような場合に補修することがあります。
• ジャンカ:材料が分離し、砂利などの骨材が偏って集まった隙間ができた状態
• コールドジョイント:先に打ち込んだコンクリートと後から打ち込んだコンクリートが一体化せず層になってしまった状態
• レイタンス:コンクリート打設の後、水分などによって上面に堆積してできる脆弱な層
工事を行う気候などの周辺環境によっても起こりやすい不備があるため、工事を行う際は最新の注意を払う必要があります。
コンクリート打設の工法

コンクリート打設の工法は主にポンプ工法とバケット工法の二種類があり、打設を行う場所や環境によって変えられています。生コンクリートは打設後に硬化が進んでいくため、場所に応じた適切な工法を選ぶ必要があります。
ポンプ工法
ポンプ工法はコンクリートポンプ車からブーム(配管)を通じて、コンクリートを押し出して流し入れる工法です。ブームを使用する場合は100メートル以上の高さがある高層ビルの上階に押し上げたり、車よりも低い地下建設物に使用されることがあります。また、ブームが使用できない場所では配管を使用して打設することもあります。
バケット工法
バケット工法は生コンクリートをバケット(容器)に入れ、クレーンで吊り上げて打設する工法です。そもそもポンプ車が入ることが難しい山間部や、ポンプ車による圧送が難しい場所で使用されています。
手押し車
大きな工事現場では使用されることが少ない工法ですが、狭い範囲のコンクリート打設においては手作業で行われることもあります。
番外編:プレキャストコンクリート
工事現場で生コンクリートを打設する従来の工法とは異なり、工場であらかじめ製造されたコンクリートを現場で設置・組み立てをする方法もあります。現場で行う作業の時間が短縮されたり、品質が安定することがメリットではあります。
しかし、型枠を工場で作成する必要があることや、コンクリートを保管しておく場所が求められることから、高コストになってしまう場合も考えられるでしょう。
コンクリート打設をする時の注意点

上記でも述べているように、コンクリート打設は周辺の環境や現場によって大きく左右されることがあります。特に気温や天候、立地によって打設時に注意するポイントが異なることには注意が必要です。
今回は場面別にコンクリート打設をする時の注意点を解説していきます。
雨の日
本来、悪天候の日程でコンクリート打設は行うべきではありません。
理由としては、コンクリートに規定以上の水分が含まれると、余剰な水分は後々蒸発しコンクリート中に空隙を生じさせます。従って、コンクリート中に空隙を生じた結果ひび割れを起こしやすくなるからです。
しかし、急な夕立や工程の都合でどうしても打設を行う必要がある場合も考えられます。
コンクリートは水分に弱いことから、雨の日はコンクリートミキサー車やコンクリートポンプ車に水が入らないようブルーシートで屋根をかけたり、水が溜まっている箇所から定期的に水を抜くことが求められます。
雨の日のコンクリート打設では、何よりも水処理を徹底することが重要です。
暑い場所での作業
暑い時期はコンクリートが固まる速度が速くなることがあります。
暑さによってコンクリートが配管内部で固まり詰まってしまった場合、配管が破裂する可能性があるため、一度配管内の掃除をすることも必要です。
また、ミキサー車の到着が遅れた場合、コンクリートが固まりコールドジョイントを引き起こす可能性もあるため、品質の低下を防ぐため、作業工程の調整を行う必要もあります。
寒い場所での作業
暑さとは反対に、寒い地域ではコンクリートが固まらないこともあります。
コンクリートが固まらないままに、表面の水分が凍ってしまった場合もコールドジョイントを引き起こすことがあるため、寒い現場ではジェットヒーターを導入することもあります。
また、積雪がある場合は雨の日と同様に水処理を行いますが、ブルーシートではなく板を使用するなど重さに耐えうる対策をすることも大切です。
狭い場所での作業
工事現場によっては人が立ち入ることが難しいほど、作業スペースが狭いこともあります。
狭い空間で長時間作業を行うことで体調不良やミスがより発生しやすくなる状況こそ、細心の注意を払う必要があります。交代要員の人員を増やすなど、周囲の状況を確認し、作業全体を考えながら進めることが求められます。
白岩工業で携わる大規模な工事

白岩工業では横浜湘南道路トンネル工事や渋谷駅再開発といったメディアにも掲載されるような大規模な工事を手掛けています。
工事現場についてはこちらでご紹介しています。
白岩工業の現場紹介 01「外環中央JCT北側ランプ(その2)工事」
若手の内から現場の管理を行う施工管理職として、大きな工事現場に関わることは求められる責任は大きいといえます。しかし、その分非常に社会性が高くやりがいのある仕事のため、成長意欲や挑戦意欲のある方であれば20代で圧倒的に成長することができます。
今の自分を変えたいと考えている人や、大規模な工事現場に関わりたいと考えている人はぜひ白岩工業へお問い合わせください。
まとめ
今回は躯体工事の中でもコンクリート打設に焦点を当てて、打設手順や工法、打設する時の注意点まで詳しくご紹介してきました。コンクリート打設作業は基礎的な知識やスキルを身に付けるだけではなく、場所や環境に応じた適切な選択が求められる作業です。
一つひとつの作業が建設物の品質に直結しているからこそ、繊細な確認作業や状況に合わせた工夫が必要となります。
白岩工業では大規模な躯体工事・コンクリート打設工事に携わっています。人々の生活を支えるインフラ設備を安心安全に長く使い続けられるように作り上げるためには、QCDSEを意識した工事であることが前提にあります。