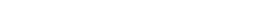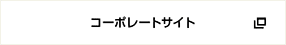白岩工業で行う躯体工事についてインタビュー!工事で気をつけているポイントをお聞きしました!
白岩工業ではダムや高速道路、鉄道工事といった大規模なインフラ設備の躯体工事を手掛けてきました。躯体工事は全ての建物の根幹を支える基礎部分のコンクリート工事になります。
今回は長年にわたり、白岩工業でさまざまな躯体工事に携わってきた根本さんに、白岩工業で行っている躯体工事や現場で工事を行う上で意識されてきたポイントまで詳しくお聞きしました。現場で得られてきた深い知見をお話しいただいたので、今後躯体工事現場に携わりたいと考えている人はぜひ最後までご覧ください。
本社土木部付工事部長・根本 勝男
白岩工業で行なっている躯体工事はどのようなものですか?
白岩工業では、主にコンクリート構造物の工事を行っています。
鉄道の切り替え工事や線路の動線を変える工事、高速道路、上下水道、発電所などの大型コンクリート構造物など、大規模なインフラ関係の工事にも多く携わっていますね。
コンクリートと聞くと地上で行う印象があるかもしれませんが、実はトンネルや、バイパス工事といった道路が交差する場所、橋梁の架替工事(古くなった橋を新しいものに取り換える工事のことですね!)などは地下や水上で行うこともあります。
躯体工事は全ての工事の基礎となる部分ですので、どの現場においても欠かせない作業です。
躯体工事の手順を教えてください。

建設物の土台は地上よりも地下で作るものが多くなっています。例えば、東京湾や地下水の水位よりも低いトンネルや、道路などが例に挙げられますね。 その場合、水位よりも低いところでものを作る場合はコンクリート構造物に水が侵入しないよう、防水工事を行います。
防水工事の基礎は専門業者さんに入っていただくことが多いので、白岩工業では防水工事後の補強から行っています。防水工事ではゴムやピット、スプレーといった加工しやすい素材を取り扱うので、それらを保護するためのコンクリートやモルタル、木製の 板を使用しています。
躯体工事を始めるにあたって防水工事を壊してしまうことがないよう、適切な処置をすることで材料が搬入できるようになります。
次に、構造物の測量とマーキングを行います。建設物を作る範囲を明確にわかりやすくするための作業を行うことで、ズレなく作業を進めることができるようになるのです。
その後、鉄筋工事で土台となる鉄筋を組み上げ、コンクリートを流し入れるための型枠工事位に入ります。型枠工事まで終了した段階で、コンクリート内部に埋め込む設備がある場合は埋め込む位置へセットする必要があります。
最終的に施工計画に沿ってコンクリートの厚みや大きさを守りつつ、コンクリートを打設していきます。打設は一度で終了する物ではないため、何度か繰り返しながら、設計図通りの躯体構造物を作り上げていくことが主な流れになりますね。
躯体工事において、QCDSEで大切にしているポイントはありますか?
まず大切なのはS:Safety(安全)の部分です。
躯体工事だけではなく、全ての現場で工事をするにあたって人が怪我をしない、機械を壊さない、物が倒れないようにするなど、安全を意識しながら、建設をすることが基本中の基本になります。
どのような作業をする場合でも、あらかじめ、「こういった危険がある」という可能性を想定しながら、施工方法と順番を決めていくことを最優先に考えていますね。
その上で、建設物において大切なのは、寸法がQ:Quality(品質)に直結することです。
作る物の大きさについては元々図面に記載されてますが、人間の手で作りあげるので、1mmも狂わずに100mのものを作ることはほぼ不可能に近いですよね。
だからこそ工事を始める前に、この範囲に収まるように作るという規格値を決めておく必要があります。図面や計画に記載することはもちろん、元請会社(お客様)と確認をした上で工事を始めています。
当社のような施工管理の仕事においては、現場の管理をする人間が規格値を理解していないと、実際工事をしている途中でミスが発生してしまう可能性もあります。現場がスムーズに進まないことは、C:Cost(原価)、D:Delivery(工程、工期)まで関わることでもあるので、とても重要ですね。
躯体工事を進める中で意識していることを教えてください。
基本的なことでもあるのですが、躯体工事のコンクリートを打設する工程では、型枠にコンクリートを入れる前に目視で確認する必要があります。
実際に現場では作られた型枠に隙間がないからこそ全く光が入らずに、底まで見えなくなります。例えば、ゴミが落ちていたり、設置 に不備があったとしてもそのままの状態では確認できない可能性が高いです。
だからこそ、コンクリート打設前に必ず照明を整備し、型枠内部の清掃やていねいな確認をした上で流し入れています。
実際に流し入れる際は、点検者という者が必ず数名おりまして、型枠の挙動や緩み、コンクリートがしっかりと角まで入っているかを目視しながら確認していきます。
近年では、人が入れないほど狭い場所やお客様が日常的に利用している駅で行うコンクリート打設工事では充填センサーやカメラを使用することもありますね。そうすると、パソコン上でコンクリートの状況が分かるので、便利ですよ。
コンクリートを流し入れる際はどのようなポイントがありますか?
コンクリートの打設はさまざまな規定に沿って行われています。
例えば、流し入れる高さにも制限がありまして、通常1.5m以内から落とすように制限されています。コンクリートは砂やセメントなどさまざまな材料が混ざっているので、高いところから落としてしまうと、重いものが下に落ちて材料分離を起こしてしまうことが考えられます。
だからこそ、事前に高さだけではなく、打設・投入箇所を明確にして作業を行っていますね。
また、誰もがコンクリート打設の深い経験を持っているわけではないので、現場では一回の打設で流し込む量がわかりやすいようにレベルポインターを使用して高さを測っています。
棒を使って色分けすることで視覚化できるのでわかりやすい目標になります。
とても細かい隙間がある時はどのように流し入れていますか?
そうですね。例えば、とても狭いところにコンクリートが流れていくと、隙間に空気が溜まってしまうこともあります。
空気の出入り口を先に塞いでしまうと、隙間がなくなることはないということですね。
なので、その場合は事前にエア抜き用の穴を開けておくことで、コンクリートが入り切ればその穴から出てくることで確認できるという方法を使用していますね。
常日頃意識されていると思いますが、万が一コンクリートの不備があった場合はどのように対応されていますか?
白岩工業で行っている大規模なインフラ工事の場合は、打ちっぱなしといわれる表面に化粧がない工事(見た目、強度の補修をしない工事)が多いので、型枠を外したら補修がないようなコンクリートに打ち上げるのが本来の仕事になります。
ただし、大小問わず不備が起きてしまうことはあるので、その場合は補修を行います。しかし、補修はコンクリートの強度や建設物の区画に関わるもので、元請さんと相談した上で許可を得て行う必要があるのです。
補修方法も強度を高めるための補修、色や見た目をよくするための補修などさまざまあります。現場によって使用する方法は異なりますが、ひとつ手間が増えるという点において、必ずお金や時間がかかるので、まずは補修がない作業を目指すことが大切ですね。
補修を行うような不備はどのようなものがありますか?
まずひとつ、先ほどもお話ししたコンクリートに入り込んでしまった空気が、表面に出てぼこぼこした状態になってしまった「痘痕(あばた)」と呼ばれるものがあります。また、材料が分離してセメントと石がそれぞれ固まってしまった不備を「ジャンカ」といいます。
その他にもコンクリートを打設していく際に、時間がかかりすぎてミルフィーユのようにコンクリートの層ができてしまう状態をコールドジョイントといいます。通常は前の層が硬化する前に打ち出し、しっかり振動機をかけると馴染むのですが、固まってしまったコンクリートに載せてしまうとうまく馴染まないことがあります。
これらの不備は、現場で気をつけるだけでは解決できない場合もあります。
不備が考えられるケースも教えてください。
都市部での作業では渋滞で次のコンクリートミキサー車が遅れてしまう可能性もありますね。コンクリートを運べる量は事前に決まっているので、打設計画の段階で進め方や必要な車の台数も分かっているのですが、状況によってはその通りに行かないことも考えられます。
その場合はミキサー車を手配する人と情報共有しながら、「今渋滞が出て何台目が遅れます」と聞いて、コンクリートの打設を1層50cmから30cmにするなど、打設回数を増やして時間を調整していきます。
コンクリート打設工事はただ届けられたコンクリートを順番に打設していくのではなく、細かな情報共有を行いながら一体となって行っていくことが必要です。
これまで根本さんが携わった躯体工事で難しい現場はありましたか?
難しく、時間がかかるのは、やはり狭い場所での作業ですね。
線路のホーム下や埋設物がある場所など、材料もなかなか供給できず、人がまともに立って歩けない場所は時間もお金もかかります。特に都市部ではすでに地下に埋まっている上下水道や電気設備をそうかんたん簡単に動かせないので、狭いだけではなく設備を破損しないように気をつける必要があるので大変でしたね。
また、昼間は人が多い場所の工事は夜しかできない場合もあります。
躯体工事を行うに当たって、必要な資格、取得した資格を教えてください。

現場によってさまざまな資格が必要とされるので、人によって取得している資格はさまざまだと思います。鉄筋工事に関わる人は鉄筋技能士、型枠工事に関わる人は型枠技能士、コンクリート施工士 など講習を受けて取得しています。
これらは専門の業者の方が取得している場合が多いので、現場を管理する私たち施工管理職の立場としては足場や作業主任者の資格になります。ただし、コミュニケーションを取りながら指示出す必要はあるので、現場の様々な知識が必要ですね。
また、安全は必ず守らなくてはいけないので熱中症予防や酸欠作業主任者といった安全に関わる資格は取得している場合が多いです。
根本さんが仕事をする上で大切にしている思いを教えてください。
どの作業においても自分の目を信じて、必ず自分自身で確認して良いものを作ることです。
人を信頼していないわけではなく、どのような仕事においても人の情報を鵜呑みにせず、自分自身の判断で責任を持って取り組みたいと考えていますね。
コンクリート打設や工事は誰でもできる仕事 ではありません。自分自身で工事に関わっているからこそ、工事において大切なところは自分でわかります。
だからこそ、自分で現場を見て、やり方を教えて、自分の目で確認する必要があると思いますね。
まとめ
今回は本社土木部付工事部長・根本勝男さんに、白岩工業の躯体工事について詳しくお聞きしました。工事現場それぞれの環境や作業において気をつけるべきポイントは大きく異なりますが、施工管理職は品質の高い建設物を安全に作るために現場を管理することが求められます。
不備や手戻りなく、QCDSEを意識しながら工事を進めるためには、さまざまな知識やスキル、経験が必要になります。だからこそ、白岩工業では未経験からでも成長できる環境を整え、新しく建設業界に携わる人々をサポートしています。
圧倒的に成長できる環境で働きたい人、自分を変えたいと考えている人はぜひ挑戦してください。